デッドライン読書会の第71回の課題図書は「アーキテクトの教科書」でした。今年の7月に発売された書籍です。
感想文
本書の概要
本書はSIerに勤める著者によるタイトル通りの「アーキテクトの教科書」です。前書きのようなものがnoteで公開されていましたので、ご案内します。
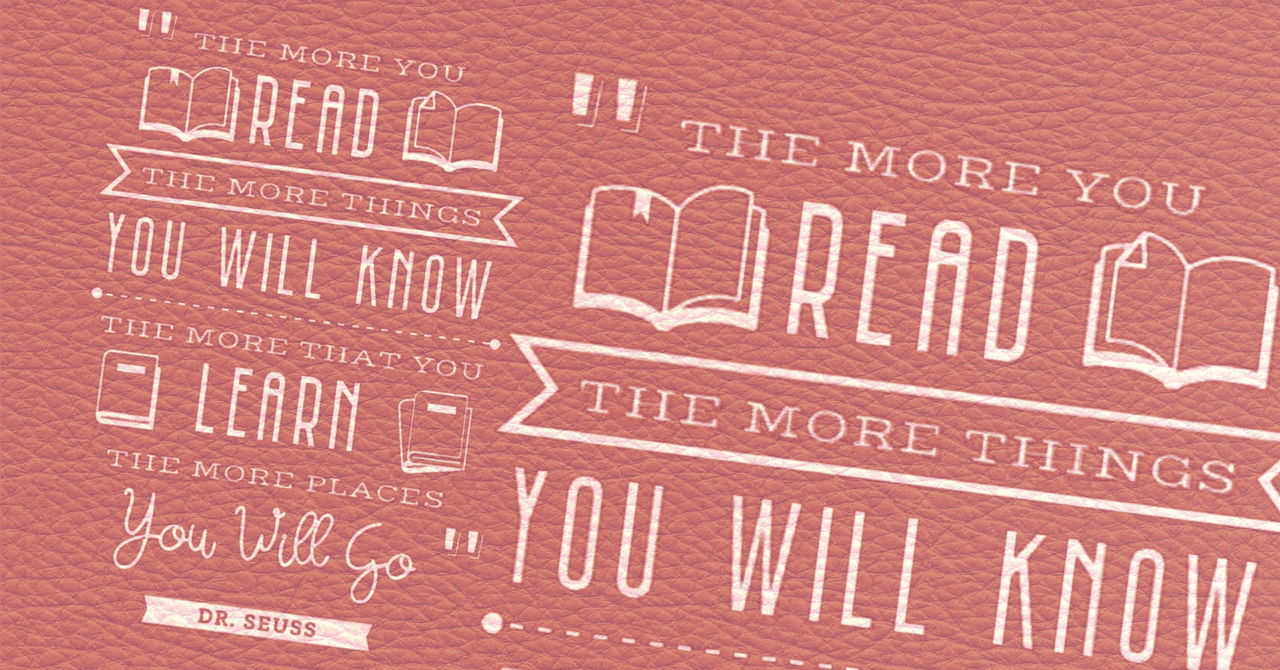
目次はこんな感じ。
- 第1章 アーキテクトの仕事
- 第2章 ソフトウェア設計
- 第3章 アーキテクチャの設計
- 第4章 アーキテクチャの実装
- 第5章 品質保証とテスト
- 第6章 アーキテクトとしての学習と成長
システム開発の順序にそい段階的に詳細化されているよな構成でした。
感想のようなもの
対象の読者
基本的にはソフトウェア開発におけるアーキテクトを目指す者に向けて書かれた書籍です。ソフトウェア開発を一通り経験した、3−4年目のエンジニアが手にすると今後の道しるべが示されています。もちろんアーキテクトではない人(プロジェクトマネージャーとか?)でもシステム開発全般の関心事について幅広く網羅されており、参考になることは間違いありません。
本書のスコープとしては品質モデル(JIS X 25010)でいう、
- 性能効率性
- 互換性
- 信頼性
- セキュリティ
- 保守性
- 移植性
に主に着目しています(といっても、機能適合性の面でもアプリケーション設計について触れられています)。
というのと、最近なかなか技術的に深堀りができていない私にもぴったりな教科書でした。この本を入口として著者がおすすめしている本を繰り返し読むっていうのが重要なのでしょう。そう有りたいです。
テーマが幅広い上に深堀りがちょうどよい
本書の特徴は教科書としてアーキテクチャに関する関心事について幅広く集めていることです。少なくとも私が知っているようなアーキテクチャに関する話題については全部取り扱われているのでは…と思いました。それぞれがキーワードだけで取り上げられているのではなく、著者の経験による事例やサンプル問題などでちょっとだけ実例が示されています。そのさらに先の背景・理論の詳細・より多くの事例に当たる場合には他の参考書へ誘導する形態が取られており、教科書という位置づけとしてバッチリだと感じました。
またただガイドするだけでなく著者の経験に基づく考え方に触れることもできます。(3章のサービス分割でのSagaパターンの議論において)
関連するサービスの数が少なく単純な場合を除いて、オーケストレーション方式を採用したほうが良いでしょう。
アーキテクトの学び方はみんな知りたい
6章では「アーキテクトの学習と成長」をタイトルとしています。エンジニアは継続的に学習する存在です。著者のアーキテクトとしての学習スタイルに触れられるのは良いですね。特に「読書マップ」という方法に興味を持ちました。これぞという技術書は繰り返し読み1枚ペラにその要約をおこなわれているようです。そしてその1枚ペラを物理書籍の表紙の裏に貼っているそうな。
そういえばこれを書いていて思い出しましたが、昔できるアーキテクトの先輩に技術書を借りたことがありました。その本には赤線がひいてあり、「この先輩はこういったところを重要だと思っているんだ…」と勉強になったことがありました。こういうのが先人の背中を見て育てっていうやつかもしれませんね。
次の本
ネクストはなんでしょうか。ワタシ的候補はこんな感じ。
- エンタープライズアーキテクチャのセオリー
- 前書を読んでいたのでこちらもぜひ
- アジャイルなプロダクトづくり
- アジャイルってことでぜひ
- 儲けの科学 The B2B Marketing
- デッドライン読書会ではないけど、私が読みたい本w



コメント